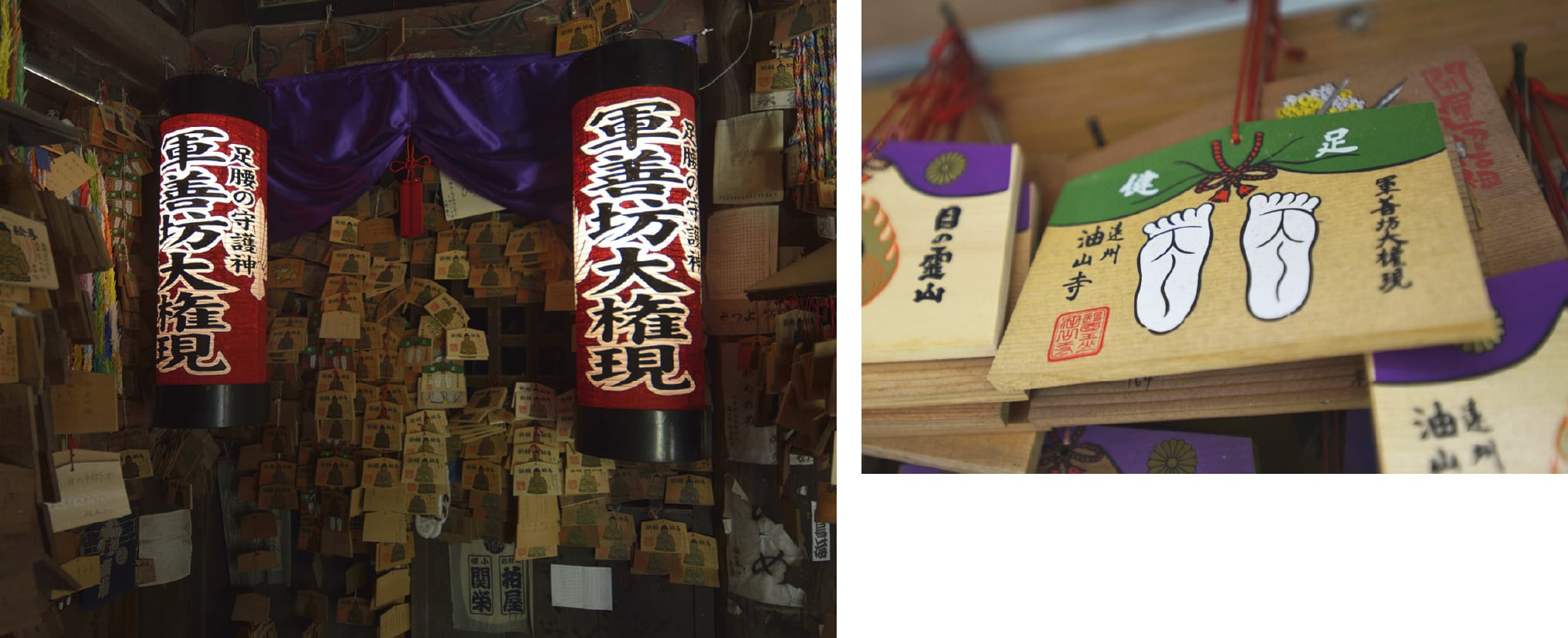医王山薬王院油山寺とは
遠州三山の一つ医王山薬王院油山寺(いおうざんやくおういんゆさんじ)は、
大宝元年(701)に行基によって開山された真言宗のお寺です。
すべての人の穏やかな暮らしと無病息災を祈り
行基は本尊の薬師如来を奉安されました。
油山寺という名前は、油が湧き出ている
「あぶらやま」に建てられていることに由来しています。